すまいの耐震診断・耐震補強(主に木造住宅)
| →お問い合わせ |
▼ 診断の種類 > | ||
| ▼ 耐震診断・補強計画の料金> |
耐震診断とは
建物の設計において、地震力に対して安全に設計することを「耐震設計」といい、その「耐震設計」をするための基準を「耐震基準」といいます。
建築基準法により、それぞれの構法毎(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造・・・)にその「耐震基準」が示されています。
現在の耐震基準は、「新耐震設計基準」と呼ばれているもので、1978 年(昭和53 年)の宮城県沖地震後耐震設計法が抜本的に見直され、1981 年(昭和56 年)に大改正されたものです。
新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害が少なかったとされており、その耐震基準が概ね妥当であると考えられています。 この「新耐震設計基準」が制定された1981 年(昭和56 年)を境に、「1981 年(昭和56 年)以前の耐震基準の建物」や「1981 年昭和56 年以降の 新耐震基準による建物」などの表現がされるようになりました。住宅やビルが地震に対してどの程度被害を受けにくいかといった地震に対する強さ、すなわち「耐震性」の度合を調べるのが「耐震診断」です。
耐震診断・耐震補強を行う目的
|  |
耐震診断・耐震補強のメリット
- 安全性の向上
- 資産価値の向上
- 将来のリスクヘッジ
- 家の地震に対する構造強度が評価(数値化)される事により、丈夫さが認識出来ます。
- 耐震診断により、どこをどう補強するか、改修の方針を設計する際の基礎データとなります。
- 補強工事の工事金額の優遇金利による融資が受けられます。
- 固定資産税などの減額措置があります。
- 補強工事の補助金(金額は行政により基準有)を受けられます。
まず、自分で診断をしましょう!
あなたの家の耐震性について、不安に思うことはありませんか? 健康診断と同じように、家の耐震診断を行ってみましょう。特に、昭和56 年以前に建築された木造軸組住宅では、耐震性の問題のある住宅が数多くあります。 まずは、専門家に依頼する前に、誰でも簡単にできる診断があります。
それが、「誰でもできるわが家の耐震診断」(国土交通省住宅局建築指導課監修)です。
この耐震診断は、ご自宅の耐震性能の理解や耐震知識の習得を進めていただき、耐震性の向上を図るための耐震改修に向けて、より専門的な診断を行う際の参考 にして いただくことを目的に作られました。お住まいになっている住宅について、住んでいる方がご自身で住宅の耐震診断を行い、住宅のどのようなところに地震に対する強さ、弱さのポイントがあるかなどがわかるようにできています。
注)この耐震診断は、国土交通省住宅局監修、財団法人 日本建築防災協会編集 のリーフレット” 誰でもできるわが家の耐震診断” を了解を得て紹介したものです。 診断内容の詳細については、財団法人日本建築防災協会へお問合せください。 なお、診断内容の無断複写、複製、転載は禁じられています。 |
さあ、診断してみましょう。
まず、下の「耐震診断を行う」をクリックしてください。診断する問診は、10 項目です。該当する項目を選んで下さい。
「誰でもできるわが家の耐震診断」 Web上で簡単に出来ます。
※一般財団法人 日本建築防災協会ホームページへリンクします。
まずは、この診断を行った後、専門家に相談してみましょう。
| 耐震診断の方法 | 対象 | 診断の精度 |
| だれでもできるわが家の耐震診断 | 一般 | B |
| 一般診断法 | 専門家 (建築士・建築関係者) | A |
| 精密診断法 | 専門家 (建築士・構造技術者) | AAA |
◆誰でもできるわが家の耐震診断 (簡易なチェック方法)
一般の人々が自ら住まいの耐震性チェックしたい場合の簡単な診断方法です. 容易に診断が出来、かつ耐震性に関する重要性をご理解頂くためのものです。
伝統的工法の住宅や3階建ての住宅は、特殊な評価方法が必要という事もあり、適用除外となっています。ここで耐震性に心配があり、あるいはより詳しく診断したい場合は、専門家による【一般診断】により診断を実施することをお勧めします。
◆一般診断法 (建築士の専門家による一般的な診断方法)
これは耐震補強等の必要があるかどうかの判定を目的としており、次の2つの方法があります。
方法1 は壁を主な耐震要素とした住宅を対象
方法2 は太い柱や垂れ壁を主の耐震要素とする伝統工法で建てられた住宅を対象
診断を行う人は、建築士及び大工などの建築に関し多くの知識と経験を有する建築関係者です。必ずしも補強を前提としない診断で、原則として内外装をはがさない調査(非破壊調査)で分かる範囲の情報に基づき診断をします。
◆精密診断法 (構造技術者、建築士による精密な診断方法)
補強の必要性が高いものについて、より詳細な情報に基づき、最終的な診断を行うことを目的としています。また補強を施すものについて、補強後の耐震性を診断することを目的としています。
診断を行う人には、建築に関し高度な知識と多くの経験が必要です。原則として建築士を想定しています。
精密診断法には次の4種類の方法があります。
①保有耐力診断法(精密診断法1)(住宅)
②保有水平耐力計算による方法(精密診断法2)(住宅、非住宅も可)
③限界耐力計算による方法(精密診断法2)(住宅、非住宅も可)
④時刻歴応答解析による方法(精密診断法2)(住宅、非住宅も可)
当社は①保有耐力診断法と③限界耐力計算による方法に対応しています。
当社が考える工事を行う最低限の目的は、震度6強程度の大地震に対して、「修復が困難な損傷はしても命を失うような倒壊をおこさないこと」です。避難することを可能とする補強をあくまで最低限の工事とし、さらに予算、要望などの状況で段階的に耐震性能を向上させる工事を行います。
具体的には1 階の上部評点をX方向Y方向ともに1.0 点以上がひとつの目安と考えています。
上部構造評点とは (日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」によります)
ここで言う評点とは、診断や改修を行なう建物が持っている強さ【保有耐力】と、大地震で倒壊しないために必要な強さ【必要耐力】との比較による値で
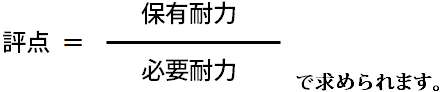
上部構造評点は、建物の耐震性を評価する値で各階のX方向、Y方向についてそれぞれ算出します。また、上部構造評点のうち最小の値を総合評価の値とします。
上部構造評点のうち最小の値 | 1.5以上 | 安全です。 |
1.0以上~1.5未満 | 一応安全です。 | |
0.7以上~1.0未満 | 補強工事を行ないましょう。 | |
0.7未満 | 補強工事を行ないましょう。 |
限られた費用で効果的な耐震改修をしょうとする場合は、一般的には、次のような優先順位で検討することが効果的と考えられます。ただし、当社では診断結果の内容によって、ここで優先順位が低くても検討し補強、改修する必要があると考えます。また、リフォーム・リノベーションを行う際に併せて実施すると効率的です。
1-1 壁の量と強さ
壁に筋交いを新たに設けたり、構造用合板を取り付けることにより、建物の地震に対する抵抗力を大きくします。開口部や壁の無い部分に新たに設ける方法と、既存の壁の強さを高める方法があります。
1-2 壁の配置
壁に筋交いを新たに設けたり、構造用合板を取り付けることにより、建物の地震に対する抵抗力を大きくします。開口部や壁の無い部分に新たに設ける方法と、既存の壁の強さを高める方法があります。
1-3 金物
柱と土台や梁、筋交いの接合部は金物等により適切に接合されていなければ効果がありません。また、これらと基礎との接合についても同様です。
ただし、不必要な箇所へむやみに取り付けても効果は上がりません。
これらは、構造要素として直接的に影響するもので、構造評点が低い場合は優先的に実施することをお勧めします。これらは相互に検討しながら改善することも必要です。
2 基礎の改善
*ここからは診断結果の内容によっては、初期の段階から検討が必要です。
上部構造が適切でも、基礎が著しく悪いと耐震性があがりません。無筋コンクリートの基礎を補強したり、地盤が軟弱で基礎が不動沈下を起こしている場合は地盤改良等により改善しなければなりません。工事費用は、高額になります。
3 屋根・壁の軽量化
瓦葺きの葺き土を取り除いたり、鋼板葺きに葺き替える他、土塗り壁を取り除きサイディングなどにし、建物の重さを軽くすることで、地震による建物にかかる水平力を減らし、建物の負担を減らすことができます。工事費は高額になりますが、老朽化した屋根の葺き替えや、大規模な壁の補強を行う場合に併せて検討すると効果的です。
4 老朽度の改善
柱や土台などの構造部材の腐れや白蟻による食害がある場合は、初期の段階で検討が必要です。外壁のクラック補修や、屋根の葺き替えや塗り替えやなどにより、構造評点が上がりますが、実質的な耐震性の向上にはあまり期待できません。長期的視野で考える場合は、放っておくと、雨漏りによる腐れや基礎の鉄筋が錆びるなどの被害をまねき、耐震性を大きく損ないます。健全な建物とするためには、リフォームと併せて検討することが重要です。また、構造評点を1.0 以上に引き上げるためには欠かせない工事です。
![]()
◆情報を収集
< まずは、情報収集からはじめましょう >
- 保管書類(新築時の建築確認書類等)の確認
- リフォーム等の履歴情報の整理
- その他参考となる事柄
雨漏り等の有無、シロアリ食害、便所や浴室等水周りの水漏等々…
![]()
◆耐震診断 打合せ(診断方法や費用等)
◆耐震診断・説明
耐震改修の必要性の有無
< 評点が1.0以上あれば一応安心です >評点とは?
< 耐震性能を把握しましょう >
- まずは一般診断法で性能を把握
- 耐震診断の結果により、建物の弱点を理解しましょう
![]()
◆改修計画の打合せ
◆補強計画の作成 ![]() 改修内容の打合せ
改修内容の打合せ
◆概算工事費の提示・耐震改修・リフォームの計画の決定
◆設計契約・実施設計(工事用の図面をより詳細に作成します)
◆工事費の提示・工期、作業内容の打合せ・決定
< 打ち合わせをしながら改修計画をたてましょう >
- リフォームと併せて耐震化を行うと、それぞれ別に行うよりコストの圧縮が可能になります。(バリアフリー化、防犯対策や設備の更新も併せて検討しましょう)
- 耐震診断の調査で把握できない場合(工事中に新たに腐朽箇所が発見されるなど)もありますので、資金的に余裕をもった計画が必要です。
![]()
◆工事契約・着手
◆工事完了・引渡し
| 一般診断法 | 図面がある場合:80,000円 図面がない場合:90,000円 |
| 精密診断法Ⅰ | 図面がある場合:150,000円より 図面がない場合:170,000円より |
※価格に消費税が含まれていません。
※以下の場合は、別途お見積もりとさせていただきます。
・延床面積150平方メートル以上
参考価格として床面積10㎡毎に+3,000円(税別)となります。
・伝統工法で建てられた木造建築
万が一、診断結果が悪かった場合は補強設計もさせていただきます。
補強設計 150,000円より(都度見積)
| 耐震診断のお問い合わせ |
診断実績




























